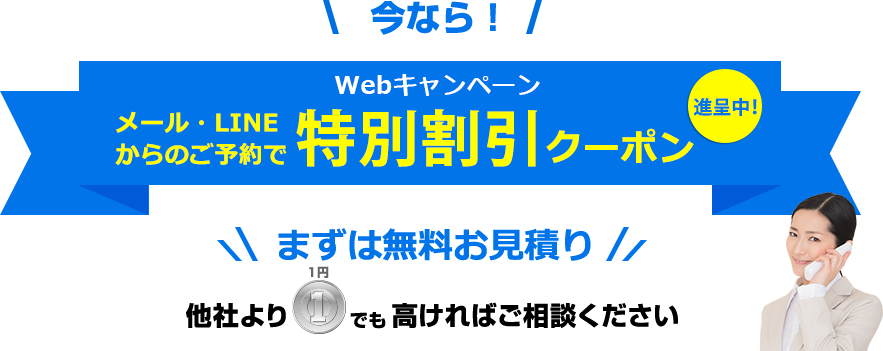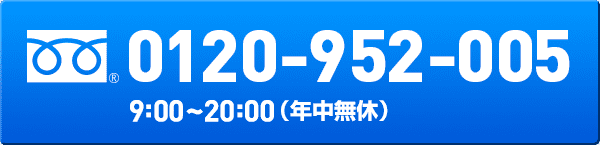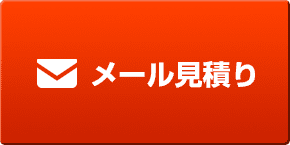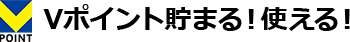2024/07/09 不用品処分不用品回収

剥製を処分する機会はほとんどないかと思われます。
もし仮にあっても遺品整理や部屋の片づけをしていくなかで親族が趣味で集めていたけど必要無くなってしまったし処分したいなという時くらいのものではないでしょうか。
処分する頻度が少ないからこそいざ処分しようと思った時、どのように処分をすればいいか分からない方が多いかと思います。
贈与や売買が許されるのか、そのまま捨てても大丈夫なのか、処分する機会がないからこそあまりよく知られていない剥製の処分方法について調べてみました。
意外と簡単?!でも難しい?剥製の処分方法3つ
剥製を処分する方法は、大きく分けて3つあります。
- 剥製を誰かに売る
- 剥製を誰かに無料で譲る
- 剥製を捨てる
それぞれの方法について、詳しく解説します。
①剥製を誰かに売る
剥製は「財力や権力などを象徴するインテリア」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
剥製にはインテリアとしての価値があり、少なからず需要が存在するため、売れる可能性があります。
剥製を売る方法は、主に2つです。
売却方法①リサイクルショップに売る
剥製はリサイクルショップで売却できます。
ただし、剥製は独特の臭いを発することから、店舗によっては衛生面の観点から買取を実施していない可能性があります。
しかしながら、リサイクルショップへ売却する方法は、一般的に無難な手段の一つです。
なお、リサイクルショップ以外にも、骨董品店で扱っていることもあります。
お近くに店舗があれば、問い合わせてみましょう。
売却方法②オークションやフリマアプリで売る
剥製はインターネット上で取引できるため、オークションサイトやフリマアプリで売るという手段もあります。
実際にオークションサイトで「剥製」と入力して検索すると、多くの剥製が出品されています。そのため、オークションサイトやフリマアプリ上で出品することも有効な売却手段です。
ただし、条例で売却してはいけない剥製もあるため、事前に調べてから出品しましょう。
剥製を高値で売るポイント
剥製を高額売却するためのポイントは、よい保存状態を保つことです。
経年劣化によって艶が落ちていたり、毛が抜けていたりする場合、買取額が低下する可能性が高くなります。
特に直射日光は剥製の大敵です。日の当たらない場所で保管して、定期的に掃除しておきましょう。
また、希少性の高い剥製は高価買取が期待できます。普段から手入れをして、綺麗な状態を保っておきましょう。
②剥製を誰かに無料で譲る
博物館や教育機関であれば、学術研究のために剥製を引き取ってもらえる可能性があります。
また、知人や友人のなかに欲しい人がいれば、譲ることもおすすめです。
剥製は学術的・芸術的な観点からみても、価値のあるものです。
コレクションやインテリアとして収集している人も多くいるため、欲しい人が見つかれば、譲渡することを提案してみましょう。
③剥製を捨てる
剥製を売却できず、譲渡先も見つからない場合は、剥製を捨てることを検討してみましょう。
しかし、剥製を捨てるといっても、どのように処分すればよいのでしょうか?
ここからは、剥製の捨て方を2つご紹介します。
捨てる方法①自治体で剥製を捨てる
剥製はほとんどの自治体の可燃ごみとして捨てられます。
扱いとしては食べ終わった魚の骨などと同類の扱いです。
大きなものでなければそのまま袋に詰めて処分ができます。
ただ、袋に入らないような大きなものは粗大ごみとして出す必要があります。
その場合は自治体に一度相談して粗大ごみとして処分するとよいでしょう。
捨てる方法②不用品回収業者へ剥製の処分を依頼する
大き過ぎて自分で捨てられないときは、不用品回収業者に依頼することがおすすめです。
そのまま捨ててしまうことに後ろめたさがあるような場合はお寺などで供養してもらうこともできます。
剥製の売却や無償譲渡は違法の場合がある

剥製によっては現在ワシントン条約によって保護されているものや国内希少野生動植物に含まれているものがあります。
希少野生動植物に指定されている種は、原則的に取引が禁止されています。
取引には、譲渡(あげる・売る・貸す・もらう・買う・借りる)が該当します。
また、取引につながる販売・頒布目的の広告や陳列も禁止されています。希少種は剥製だけでなく、生きている個体や死体も規制の対象に含まれます。
違法な譲渡を行った場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられることがあるため注意しましょう。
国際希少野生動植物を守る種の保存法
例えばウミガメの全形を保持したものや象牙は登録票なしに取引できません。
登録が無いものに関しては、未登録での売買はできないと考えた方がよいでしょう。
ごく稀ですが、規制前に剥製になったものがあります。その場合も譲渡や売買は禁止されています。
また、剥製以外に毛皮やハンドバッグのように加工されていても規制の対象となるため注意が必要です。
登録がないと違法になる動物の種類
希少野生動植物種は「国内種」と「国際種」の2つに分類されます。
<国内種の例>
- トキ
- イリオモテヤマネコ
- ハヤブサ
- タガメ など
<国際種の例>
- ジャイアントパンダ
- アオウミガメ
- アフリカゾウ
- アジアゾウ など
これらの希少種は、基本的に許可や届出、登録を行わなければ取引できません。
つまり、売却・譲渡する対象物が希少野生動植物に該当していなければ、手続きを行う必要はありません。
希少種に該当するかどうかがはっきり分からない場合は、関係各所へ事前に問い合わせ、取引の可否を確認しましょう。
★詳細は環境省のHPをご確認下さい⇒剥製の譲渡し等の規制及び手続きについて
種の保存法に違反すると罰則がある
登録証を確認して、保護認定されているか確認してみましょう。
もし該当する場合は環境省に申請して博物館や大学、動物園等に寄贈できる可能性があります。
何も知らずに売買をしたり譲渡をしたりすると罰せられます。知らなかったからと言って許されるものではないので十分注意しましょう。
■平成25年の法改正以降罰則
<違法な捕獲等、譲渡し等、輸出入の場合>
- 行為者:5年以下の懲役又は
- 500万円以下の罰金
- 法人:1億円以下の罰金
<販売目的の陳列と広告>
- 行為者:1年以下の懲役又は
- 100万円以下の罰金
- 法人:2,000万円以下の罰金
非常に厳しい内容となっているため、剥製の取り扱いには十分に注意してください。
出典:デジタル庁「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
登録の手続き方法と費用
希少野生動植物の取引は原則禁止されています。
ただし、登録要件に該当する種については、登録機関から登録票の交付を受ければ取引可能です。
登録申請は、一般財団法人自然環境研究センターに問い合わせて、申請書類を作成しなければなりません。
書類に必要事項を記入した後、同センターへ提出して、受理されれば登録票が交付されます。
生体や剥製の場合、手数料は1個体につき5,000円です。
また、象牙から製造された製品は認定申請を行うことで、標章の交付が受けられます。
標章は、適正に入手された象牙から作られたものであることの証です。
認定対象は、印章・装身具・楽器・仏具などです。標章交付の手数料は、1個につき60円です。
結局のところ、どうすればいいの?

①状態が良ければ売る
状態が良いものであれば自身でオークションに出してみたり、リサイクルショップなどに持ち込んでみたりしましょう。
指定保護等されていないか、登録票などがあるかをよく確認してから行ってください。
②希少価値のあるものは譲る
希少価値のあるものだった場合は、博物館や大学等で受け入れてもらえるか問い合わせてみましょう。
学術研究や芸術品として価値があれば、展示してもらえる可能性があります。
③指定保護がなければ捨てられる
もし剥製と一緒にラベル(種類・製造日が記されている)がある場合、確認して特に指定保護等されていなければそのまま処分できます。
自治体の可燃ごみの袋に入る場合は可燃ごみとして捨てられます。大きなものであれば粗大ごみとして各自治体に沿った処分方法を行い、もし後ろめたさがあるようであれば一度供養してもらいましょう。
【弊社事例】剥製を含む不用品の回収事例|名古屋市守山区

名古屋市守山区では、家屋解体前の片付け作業をご依頼いただき、剥製を含む不用品の回収作業を行いました。
ベッドや棚、障子などとあわせて剥製を回収して、剥製部分と木製品に分別いたしました。
名古屋市近郊で剥製を含む不用品回収はグッドサービスへご相談ください

名古屋市近郊で剥製の回収をご希望の方は、グッドサービスにお任せください。
※回収できない場合もございます。
「剥製が大きすぎて、自分では処分できない」とお困りの方は、お気軽にご相談ください。
ただし、剥製の売却や譲渡は、条例によって違法となる可能性がございます。
【こちらの記事もおすすめ】